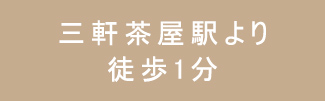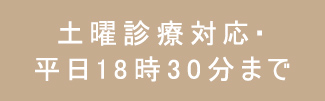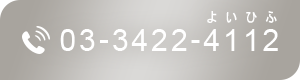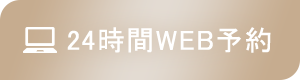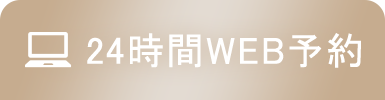小さないぼ・できものとは?
 「いぼ」や「できもの」と聞くと、多くの方が「皮膚にポツンとできたもの」を思い浮かべます。しかし、いぼにも様々な種類があり、単なる皮膚の盛り上がりなのか、ウイルス性のものなのか、注意すべき疾患なのかを見極めることが大切です。
「いぼ」や「できもの」と聞くと、多くの方が「皮膚にポツンとできたもの」を思い浮かべます。しかし、いぼにも様々な種類があり、単なる皮膚の盛り上がりなのか、ウイルス性のものなのか、注意すべき疾患なのかを見極めることが大切です。
小さないぼ・できものの特徴
- 良性のものが多いですが、まれに悪性のケースもあります。
- 首や顔、手足にできやすいです。
「ただのいぼ」ではなく、
適切な診断が必要
いぼやできものの種類によっては、自然に消えるもの、治療が必要なものがあるため、自己判断は避けましょう。
小さないぼ・できものの症状
いぼやできものは見た目が似ていても、発生原因や性質が異なります。以下の特徴を参考に、自分の症状がどれに当てはまるか確認しましょう。
よく見られる小さないぼ・できもののタイプ
|
種類 |
主な症状 |
できやすい部位 |
|---|---|---|
|
尋常性疣贅(じんじょうせいゆうぜい) |
表面がザラザラしている |
手足・指・ひざ |
|
扁平疣贅(へんぺいゆうぜい) |
平らで小さい・増えることがある |
顔・腕・手の甲 |
|
アクロコルドン(スキンタッグ) |
柔らかく小さい突起がある |
首・脇・まぶた |
|
脂漏性角化症(老人性いぼ) |
加齢による皮膚の変化で黒っぽい |
顔・背中・手の甲 |
|
粉瘤(アテローム) |
皮膚の下にしこりがある・膿が溜まることがある |
背中・顔・耳の裏 |
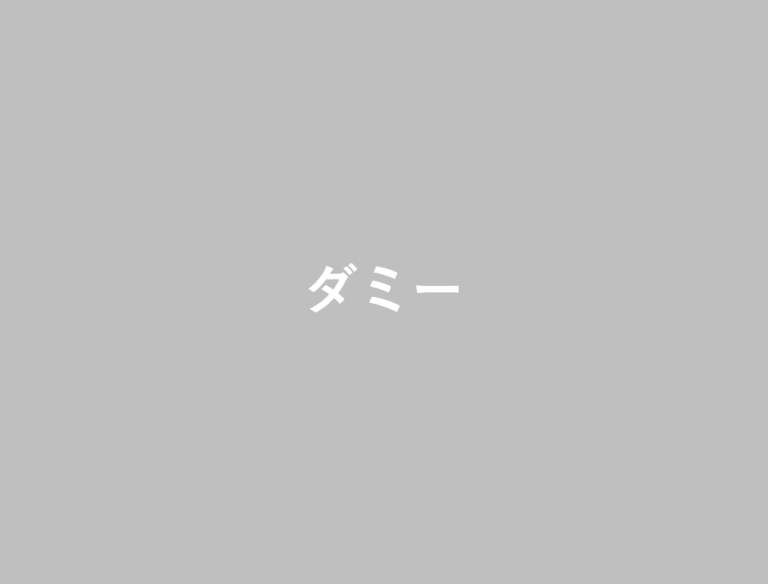
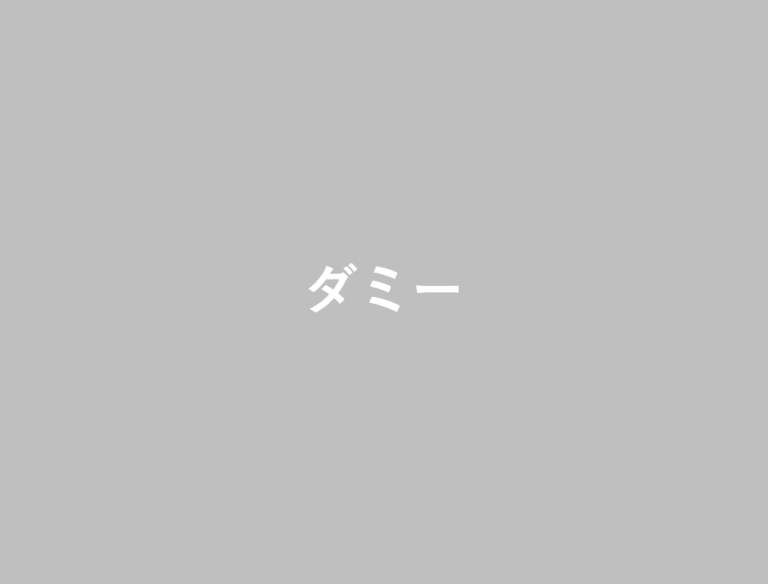
小さないぼ・できものの原因
 いぼやできものは、様々な要因で発生します。原因を知ることで、予防や早期対処が可能になります。
いぼやできものは、様々な要因で発生します。原因を知ることで、予防や早期対処が可能になります。
主な原因
ウイルス感染
(ヒトパピローマウイルス)
尋常性疣贅など、ウイルス性のいぼは感染する可能性があるため注意が必要です。
加齢や皮膚の老化
脂漏性角化症やアクロコルドンは年齢とともに増えます。
皮膚への刺激・摩擦
首元や脇にできやすいスキンタッグは、摩擦が主な原因となります。
毛穴の詰まりや皮脂の分泌異常
粉瘤は皮膚の中に皮脂が溜まることでできます。
小さないぼ・できものの検査
「このできものは何?」「放置して大丈夫?」と不安になる方も多いと思います。診察では、次のような方法で検査を行います。
検査方法
視診(肉眼でのチェック)
形や色、硬さを確認し、ウイルス性かどうかを判断します。
ダーモスコピー(拡大鏡)検査
 表面の模様や内部構造を詳しく観察し、悪性の可能性を確認します。
表面の模様や内部構造を詳しく観察し、悪性の可能性を確認します。
病理検査(組織診断)
※必要に応じて
切除した組織を顕微鏡で調べ、皮膚がんなどのリスクを確認します。
小さないぼ・できものの治療
いぼやできものの治療方法は、種類や症状によって異なります。
主な治療方法
|
治療法 |
適応する症状 |
特徴 |
|---|---|---|
|
液体窒素(凍結療法) |
ウイルス性いぼ |
低温で凍らせて除去します。複数回施術が必要です。 |
|
プラズマペン |
スキンタッグ・脂漏性角化症 |
傷跡を残さず除去しやすいです。 |
|
レーザー治療 |
扁平疣贅・老人性いぼ |
色素のある部分を完全に除去できます。 |
|
外科的切除 |
大きめの粉瘤・腫瘍 |
根本から取り除くため再発防止に繋がります。 |
小さないぼ・できもののよくある質問
小さないぼは自然に治りますか?
いぼやできものは放置すると悪化しますか?
いぼ取り治療は痛いですか?
保険適用されますか?
いぼができやすい人の特徴とは?
いぼは誰にでもできる可能性がありますが、特定の条件が重なると発生しやすくなります。「気がついたらいぼが増えていた」「なぜ自分ばかりできるの?」と悩む方も多いのではないでしょうか。いぼができやすい人の特徴は以下となります。
免疫力が低下している人
免疫力が低下すると、いぼの原因となるヒトパピローマウイルス(HPV)に感染しやすくなります。
免疫力が低下する主な原因
疲労・ストレス
仕事や家事の負担が大きいと免疫力が落ちます。
睡眠不足
6時間未満の睡眠が続くと免疫細胞の働きが鈍ります。
栄養バランスの乱れ
ビタミン不足(特にビタミンC・ビタミンD)が影響します。
過度なダイエット
食事制限が免疫機能を低下させます。
予防策
規則正しい生活を意識し、栄養・睡眠をしっかり確保しましょう。
皮膚に傷がある人
皮膚に傷があると、そこからHPVが侵入しやすくなり、いぼができやすくなります。
感染しやすい場面
- 転倒して膝を擦りむいた時
- カミソリで肌を剃った時
- 虫刺されをかきむしった時
特に、足裏の傷はウイルス性いぼ(足底疣贅)につながることが多いので注意が必要です。
予防策
肌に傷を作らないよう気をつけ、傷ができたら早めに消毒しましょう。
HPVに頻繁に接触する人
いぼの原因となるヒトパピローマウイルス(HPV)は、直接・間接的に感染するウイルスです。
感染リスクが高いシーン
- 公共のプール・ジム・銭湯を利用する(足の裏で感染しやすい)
- ヨガマットやバスマットを共有する
- 直接いぼに触れる(家族や友人との接触)
HPVは目に見えないため、知らないうちに感染していることが多いのが特徴です。
予防策
タオルやマット類を共有しない・公共の場ではスリッパを履くなど、接触を減らしましょう。
爪を噛んだり、
甘皮を剥いたりする人
爪噛みや甘皮剥ぎの習慣がある人は、指先に小さな傷ができやすく、そこからHPVが侵入するリスクが高まります。
指先のいぼ(手指疣贅)が
できやすい人の特徴
- ストレスや緊張で無意識に爪を噛む
- ネイルケアの際に甘皮を取りすぎる
- 指先の皮膚が乾燥しやすい(あかぎれ・ひび割れ)
予防策
爪噛みをやめるために、指先の保湿やストレス対策を意識しましょう。
家族にいぼができやすい人がいる(家族歴)
いぼはウイルス感染が原因ですが、家族内で発生しやすいことがあります。
家族内でいぼができやすい理由
- 体質的に感染しやすい(免疫の遺伝的要因)
- 同じ生活環境を共有している(タオル・バスマット・靴など)
予防策
家族内でタオルやスリッパを共有しない・いぼができたら早めに治療しましょう。
肥満体質の人
肥満の人はいぼができやすいといわれています。特に首や脇、太ももの付け根に小さないぼ(スキンタッグ)ができることが多いです。
肥満といぼの関係
- 皮膚同士の摩擦が増える(スキンタッグができやすい)
- 汗をかきやすく、細菌・ウイルスが繁殖しやすい
- 皮膚の新陳代謝が乱れ、いぼができるリスクが高まる
予防策
適度な運動やスキンケアを心がけ、皮膚の摩擦を減らしましょう。